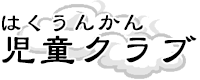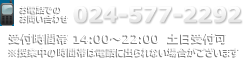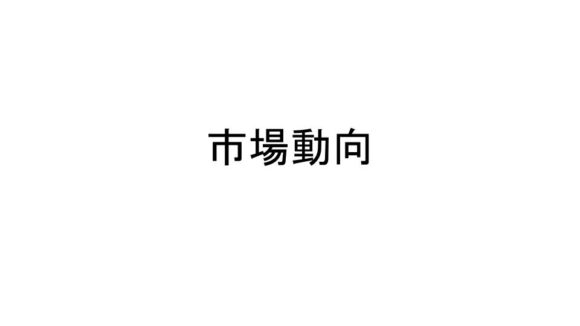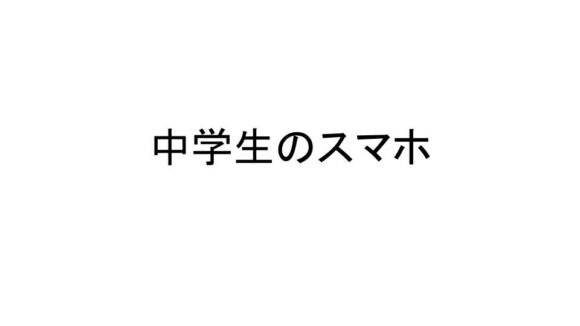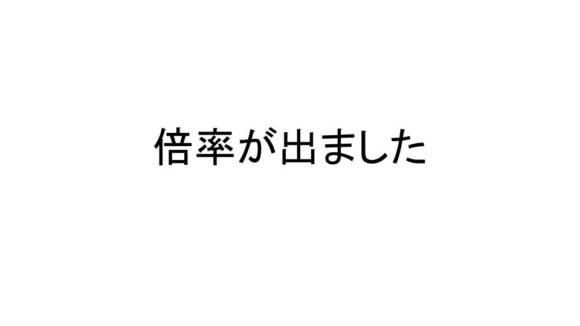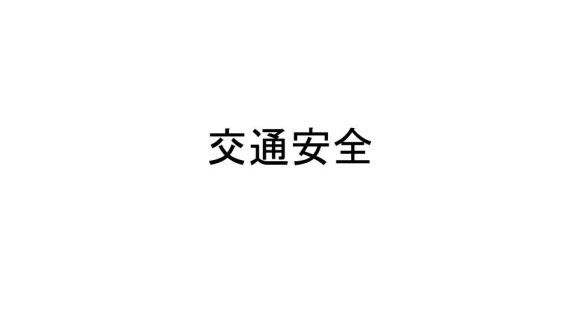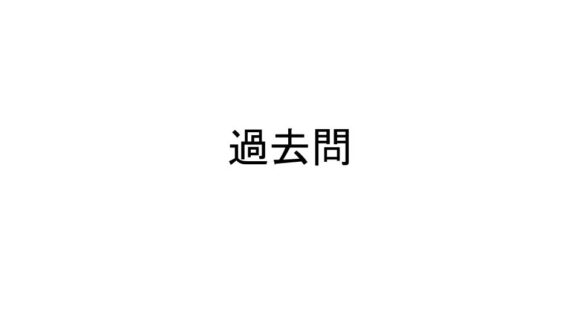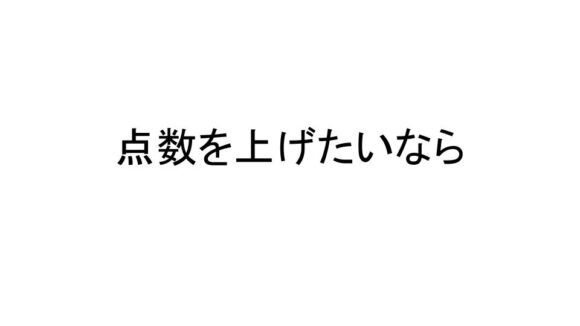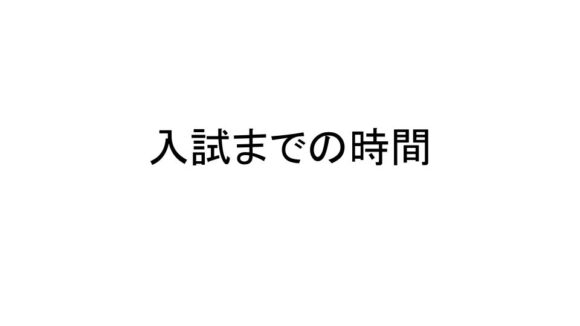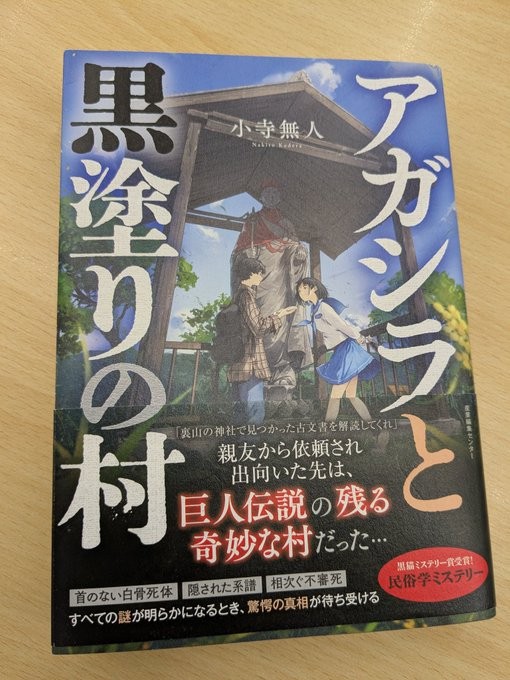公立高校併願制
投稿日:2026年2月20日
2月20日 快晴の福島伊達
高専の合格発表
無事通過してくれました。
中1の頃から希望していて、
ずっと努力する姿を見てきたので。
彼の努力の勝利です。
さて、公立高校併願制、の話
高校授業料無償化が進んで
私立高校を志望する人が増えました。
授業料だけの支援ですが、
それでも私学の魅力もあり、
公立高校離れが加速しています。
そうした影響からか、
公立高校の倍率低下が課題となっています。
福島県でも1倍を切り、
選ばなければ誰でも公立高校に行ける、
という状態です。
(福島県では1倍割れでも不合格があります)
福島県ではないですが、
公立高校を複数選択できる制度が
検討されているようです。
第二希望までを選択し
公立高校合格者を増やそうという
算段のようです。
たとえば、
第一志望を福島、第二希望を橘とし
福島高校が不合格だった場合でも
第二希望の橘に受かれば
進学できる、ということでしょうか。
仮に公立高校併願制とし
こうした制度が実現したら、
どうなるんでしょう。
難しい高校への挑戦が増える?
橘が第一志望の生徒が
福島高校が不合格だった生徒に
押し出される?
私立高校への併願は減るか?
公立不合格による私立進学が
大幅に減ってしまうと
私学経営は成り立つのか?
実現に向けて
考えなければならないことは
山積みのようです。
個人的には、
公立高校を減らすのが
少子化の現状では自然だと
思うのですが。
難しい問題です。
今後の他県の制度変更に
注目していきたいです。