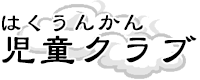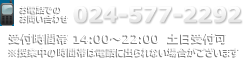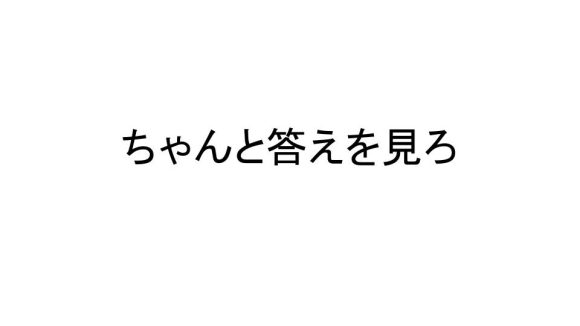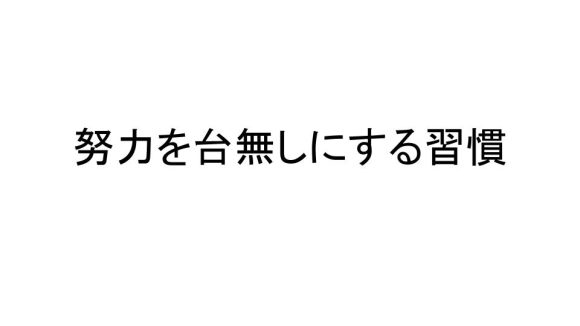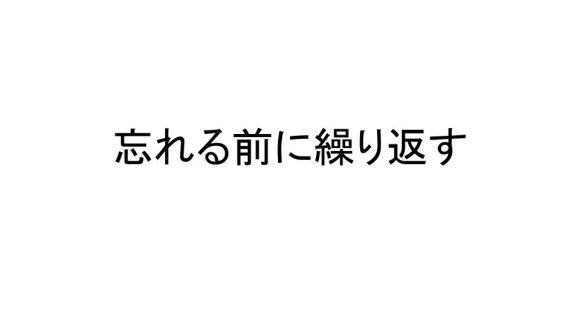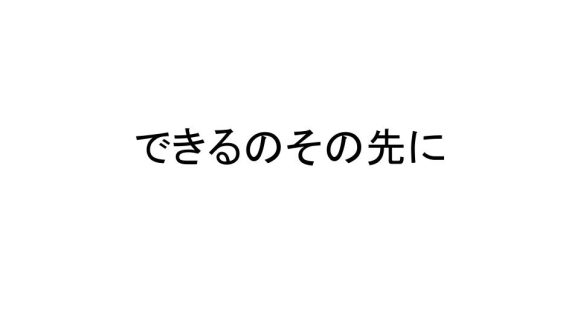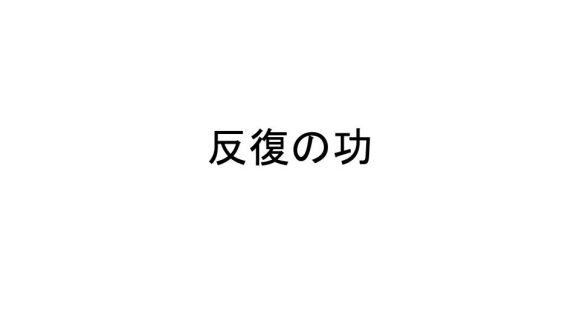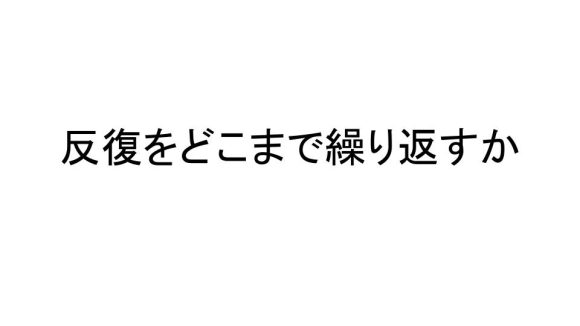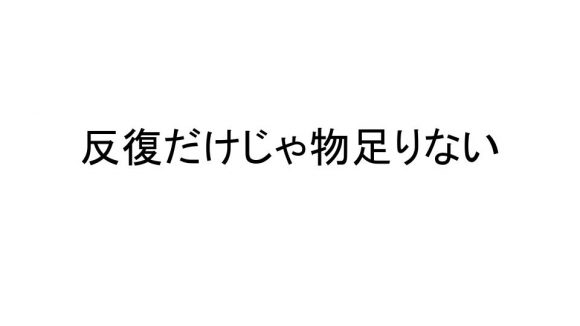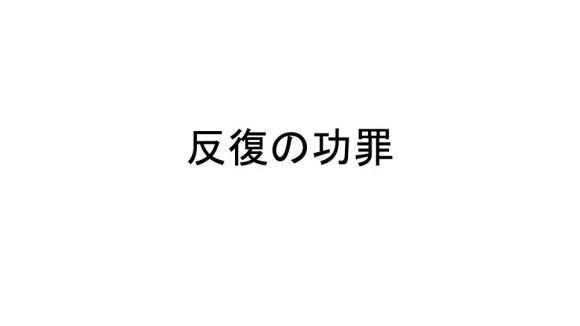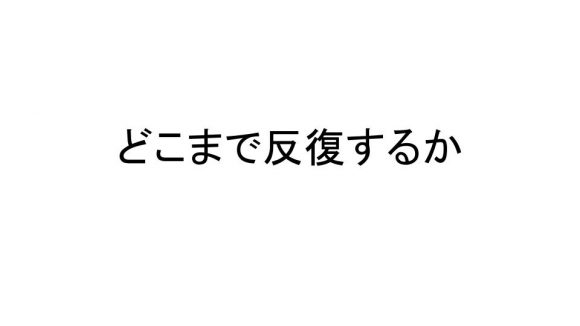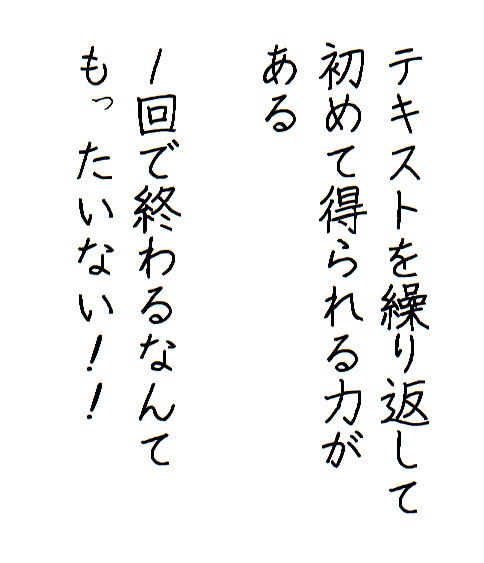30度超えの福島伊達
今日は大学生と町づくりのイベント準備。
だんだんと形作られていく様を
一緒に作れることがうれしい。
さて、学童では勉強の時間を設けています。
宿題と自学をするわけですが、
「テストがあるんです」なんていう日は
テスト範囲のプリントに挑戦したりします。
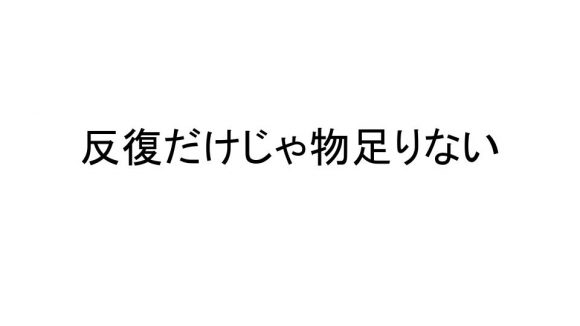
3ケタ÷1ケタの割り算、余りも出る問題。
80問ほど。
自分で丸付けまでして30分くらいですかね。
スラスラです。goodです。
だって毎日やってますから。
計算は、筋トレと同じで反復によって確かになります。
だけど、それだけじゃ足りません。
計算力は学年を超えて
身につけることはできても、
先取学習でしかありません。
追いつかれるものです。
頭がいい、というのは
単に計算力があるだけではなく、
分からないものを調べたり、
できないことを克服したり、
そういった面倒くさいことを
厭わずできることに変わっていきます。
基礎基本の徹底が、
先々の学びにつながるように
何かできないか思案中です。
よし、志事すんぞ!
さぁ、いきましょー♪
テスト対策 テキストは1回で終えるものではない理由
今日は過ごしやすい福島伊達。
代表渡邉が更新です。
部活動が本格化してきて、
基礎の練習に明け暮れる1年生。
難しいことをしたがる生意気な1年生を
ボスゴリラみたいな先輩がたしなめる、
そんな風景を
スラムダンク世代は思い浮かべてしまいます。
何度も繰り返すこと、
その反復が確かな力を生みます。
学校や塾から渡されたテキストも
最初から書き込むのは、もったいない。
いや、愚行ともいえます。
1回で終えるものではないのです。
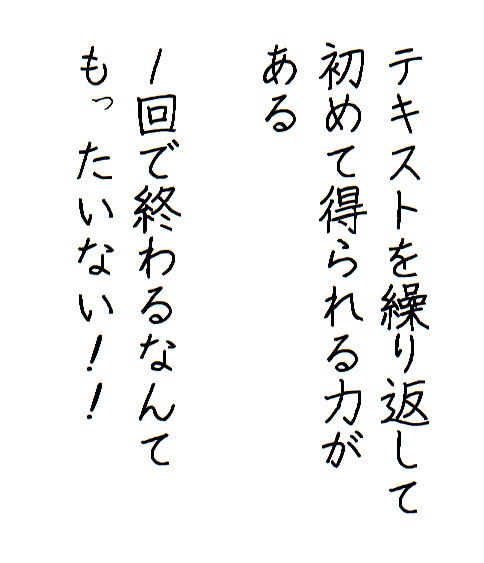
理由その1
~1回目の勉強は、
できないところを見つける勉強だから~
1回目は間違えることが多いです。
理科や社会は調べないとできないものもあります。
英語や国語は、分かってるけど
書けない単語や漢字が出てきます。
1回目は間違えやできないところを見つけて
練習すべきものを探し出すためのもの。
書き込んだら、
次に覚えたかどうか確認しにくくなります。
オススメは
1回目の間違った問題に印をつけます。
2回目は、その印の問題だけノートにやります。
できたら、印を消してもいいですし、
またできなかった問題に、別な印をつけてもいいです。
消すにせよ付けるにせよ、
全部できるようになったら、
ようやく書き込み。
理由その2
~繰り返すべきタイミングを待つため~
中学校からもらったテキストは、
提出しなければならないので、
書き込まざるを得ないのが残念ですが、
塾のテキストなら、
書き込まなくていいです。
中間テストの勉強でテキストを使いました。
そしたら期末試験までの間に
復習をしてほしいんです。
期末テストも終わりました。
そしたら夏休みに
復習をしてほしいんです。
2学期3学期、普段の勉強で
復習をしてほしんです。
何度も何度もくり返し使って、
書き込みをして、
自分だけの問題集にしてほしいんです。
高校生になって
大学入試を志したなら、
何度もテキスト対話を重ねる勉強が必要です。
そのための、練習にしてください。
ちなみに、2回目3回目のくり返しでは、
正確性とスピードを意識してください。
よし、志事すんぞ!
さぁ、いきましょー!