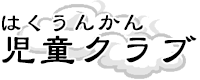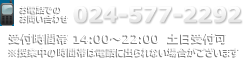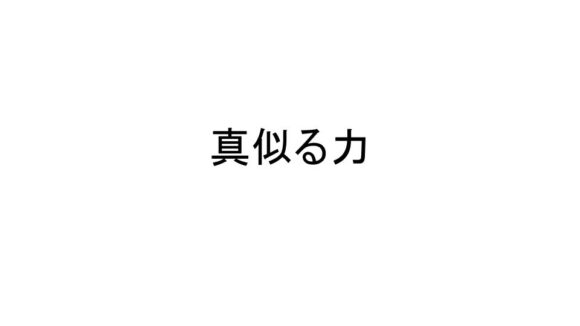真似る力
投稿日:2025年10月10日
10月10日 秋空の福島伊達
今日は10月10日です。
昭和の人間にとっては
休日感があります。
ちなみに令和7年は
昭和100年にあたるので
今日は
昭和100年10月10日だそうです。
さて、真似する力、の話
先生の物まねをする生徒は
クラスの人気者でしたよね。
うまく特徴や口調を掴んで
そっくりにまねる。
懐かしい先生のお顔が浮かびます。
この真似する力は
勉強にとって大事な要素になります。
幼児期は
大人のまねごとをして
言葉を覚え、
社会生活に必要な
衣食住のルールを身に付けます。
学童期に入ると
音としての言語から
文字としての言語習得期に移り、
仮名や漢字を覚えていきます。
また、同じ形、違う形という
図形の認識であったり、
いぬ、野菜、職業といった
言葉の分類も複雑になる中、
同じ、似ている、違う、といった
判断をしていきます。
これもまた
特徴を掴む=まねる、が
成せる行動だと考えます。
中学生になると
学習内容が複雑になっていきますが、
そこでも
真似る力は活かされていきます。
方程式を解くまでの手順、であったり
英語の文法を確認事項に倣ったり
上手な作文を参考にしたり、
あらゆるところで
真似る力が必要です。
それぞれの発達段階に合わせて、
真似る力が必要な課題があります。
その時々で練習し、
クリアをしていくことで、
学習が進んだ時に習得しやすくなります。
逆もまたしかり。
ちゃんと身に付けないから
苦労しているな、と
見受けられる人もいます。
武道の世界では
守破離、という言葉がありますが
それこそ
初心者は型を守る、
手本を忠実に身に付けることが
求められます。
真似る、守る、その力は
独学で身に付けるのは
なかなか難しいぞ、と思うのです。
大人の確認、先達の指導が
上達を加速させるのは、
そうした理由があると思いました。
志事すんぞ!
- «前ページ